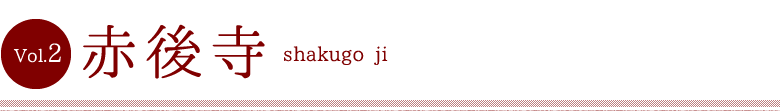インタビューは2017年8・9月に実施
腕を失い、手を失い、頭上の十一面を失くした痛ましいお姿。歴史上何度も戦場となったここ湖北の地で、赤後寺のお堂は焼失しても観音さまだけは村人によって運び出され、今に受け継がれてきた。先祖が必死に守ってきた観音さまを、地域一丸となって大切にしている高月町唐川地区。
2017年度の世話方さん6名に集まっていただき話を聞いた。
左から、布施さん、中川さん、山田さん、津田さん、宮崎さん、雨森さん

こちらの参拝は事前予約制ですよね?
布施さん: はい。事前に電話で予約をいただき、その日の当番が応対します。毎日交代で当番をする世話方は全部で6名で、2年任期。毎年自治会の選挙で3名ずつ新しく選ばれ、2年目の人が1年目の人に任務内容を伝えるというかたちを取っています。
赤後寺、日吉神社、稲荷神社がひとつの境内の中にある神仏習合の様式を残す

任務内容を教えてください。
布施さん: 毎日の当番は、朝、扉を開け、掃除をしてお勤めをし、参拝者を迎える準備をして、夕方にはお勤めと戸締り。そして、予約応対用の携帯電話を翌日の当番の家へ届けます。その他、月に一度の法要と、毎年7月10日の千日会法要の準備と当日の運営ですね。千日会は他府県からも多くの方が来られるので、村じゅうで大掃除をして準備と運営にあたります。
津田さん: 我々とは別に、村の者が交代で、おぶくさん(御仏飯)とお水を毎日お供えに来ることになっています。寺の他に、境内にある日吉神社と稲荷神社にも洗米や塩、水を朝上げて、夕方下げる。これも1年の当番表があるんですよ。

地域全体で守られているのですね。
津田さん: 無住職で無宗派なので、寺も神社もまとめて唐川地区の氏神さんなんですね。村の人にとって、今も生活の中に信仰の仏さまが根付いていると思います。朝の5、6時に毎日お参りに来られる方も何人かおられますよ。

年間を通して、どれくらいの参拝者が来られますか?
布施さん: 千日会やお祭りを入れて4000人くらいです。個人の方については、3割が関東から、というのが特徴的ですね。2014年に東京で展覧会(観音の里の祈りとくらし展)をしてから、現地を見たいと言って来られる方が増えたんです。
左 千手観音立像(9世紀・国指定重要文化財)
右 聖観音立像(10世紀・国指定重要文化財)

美術館で見るのとお寺で見るのとでは全然違うでしょうね。
布施さん: この環境に溶け込んでいるのが魅力というふうにおっしゃいます。「匂い」といいますか、観光地化されていないのがここの魅力かもしれないです。
宮崎さん: 皆が交代でお守りしてるんです、なんて言うとびっくりされるもんな。

本当に、よくこれだけのことができるなあと思います。
宮崎さん: 当たり前やと思っているんで、改めて聞かれるとどう説明していいかわからへんなぁ。
雨森さん: 「当たり前」ということにびっくりされる。でも、我々は観音さまを守ってるというのではなく、守らせていただいている、見守っていただいていると思ってるから、苦労やとは思わへんなぁ。

参拝者の方々へ、お寺の説明もされているとか?
津田さん: ある時、古い書物や昔から村に言い伝えられていることをもとに先輩が文章をこしらえてくれたんです。案内に統一性がないと具合悪いと言って。それを、自分が説明しやすいようにアレンジして使っています。
布施さん: 私は今年から当番をするようになって初めて、観音さまのことを詳しく知りました。それまでは、ただ手を合わせる仏さまでしたから。
宮崎さん: 我々よりも、参拝に来られる方のほうが詳しいもんなぁ。
安土桃山時代の厨子の中に安置される。日光東照宮の陽明門と同じ様式
布施さん: 物見遊山(ものみゆさん)の方は少ないですね。毎月来られる方も何人かおられますよ。
津田さん: 真っ暗にして線香を立てて20~30分じっと拝んで帰られたり。無宗派ですから、好きなように拝んでもらったらいいんです。「胸がスーッとした」と言われたりします。皆さん「ありがとうございました」と言って帰られるのがありがたいですね。
雨森さん: 「修復されないのですか?」と聞かれることもあるけど、現状の観音さまが一番いい。この場所で、この観音さまに会っていただきたいですね。